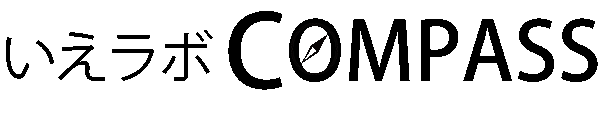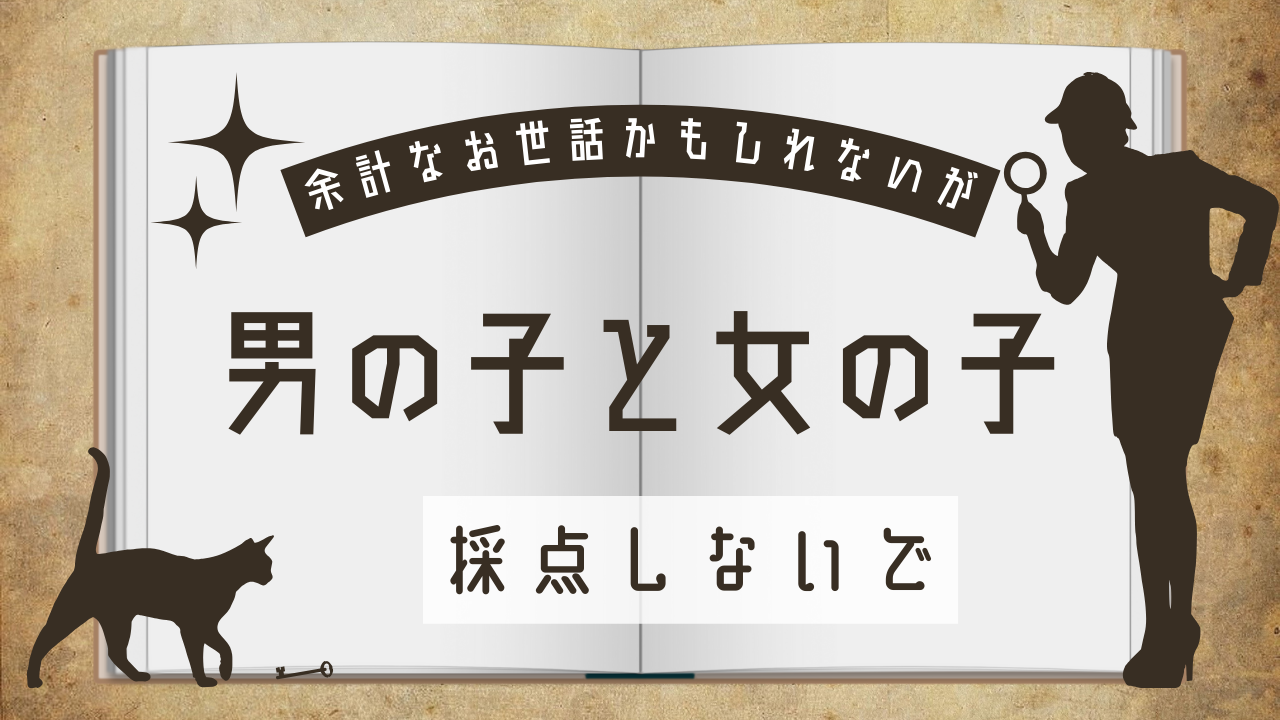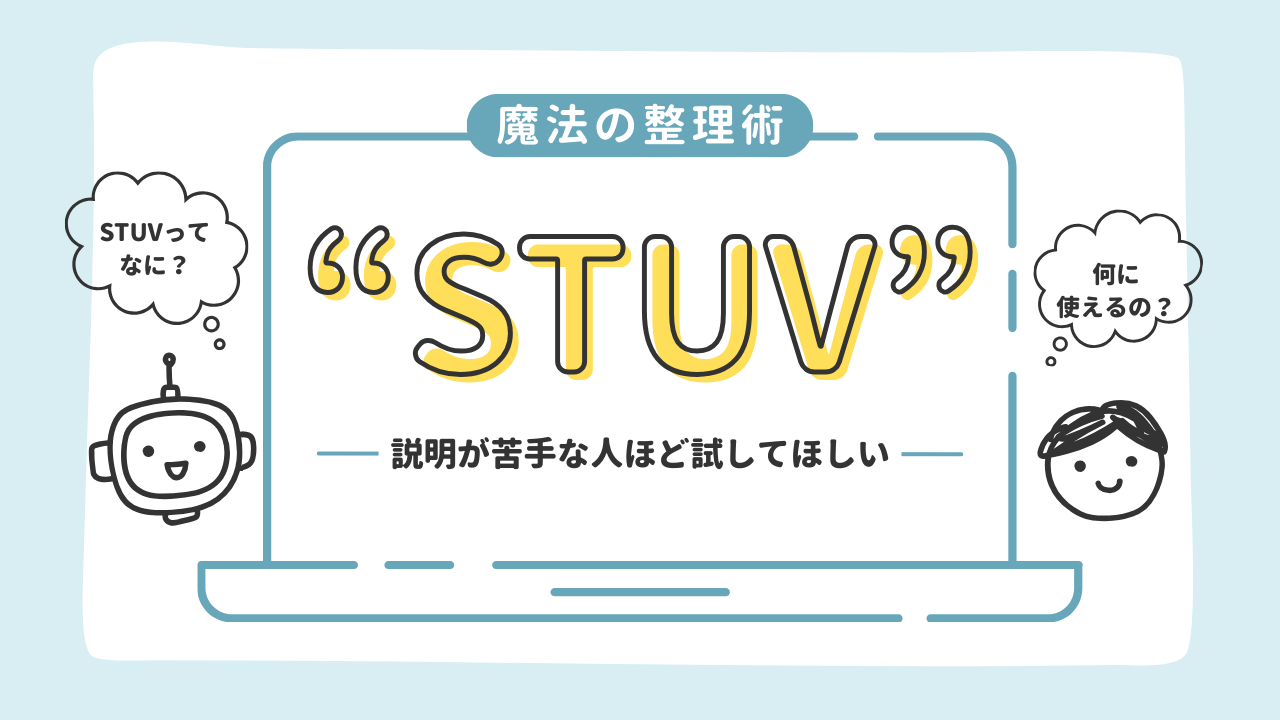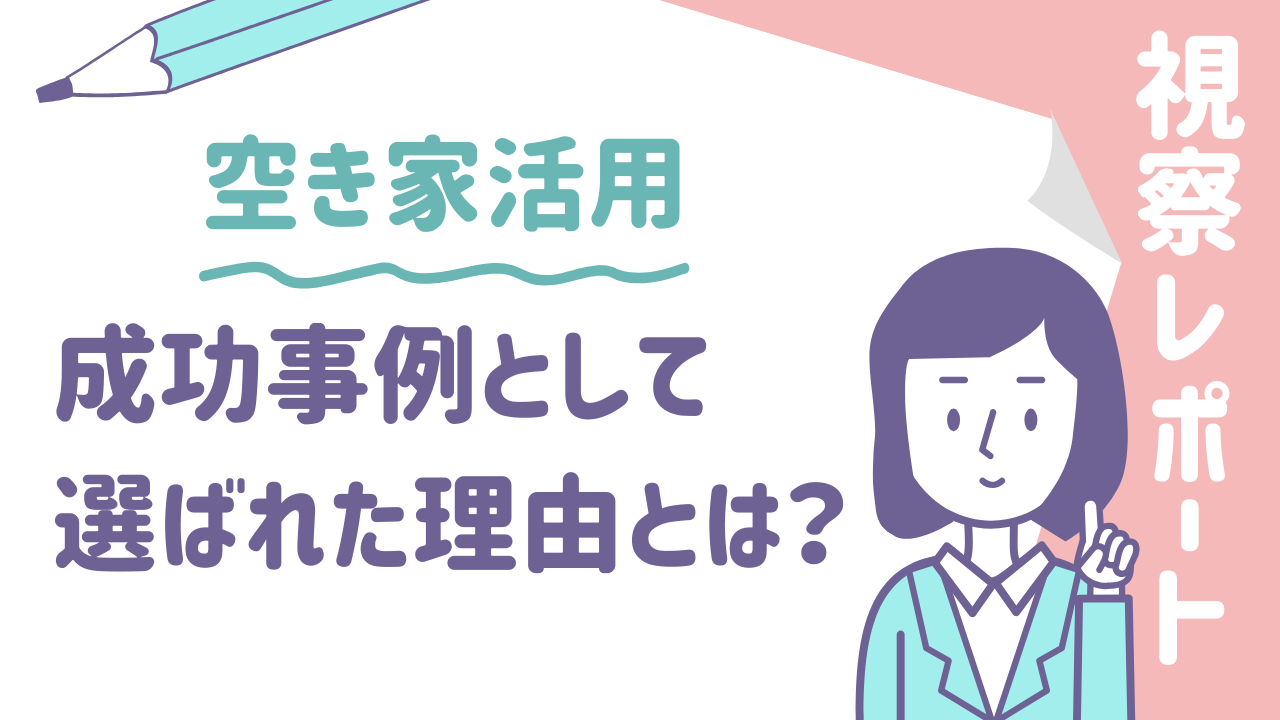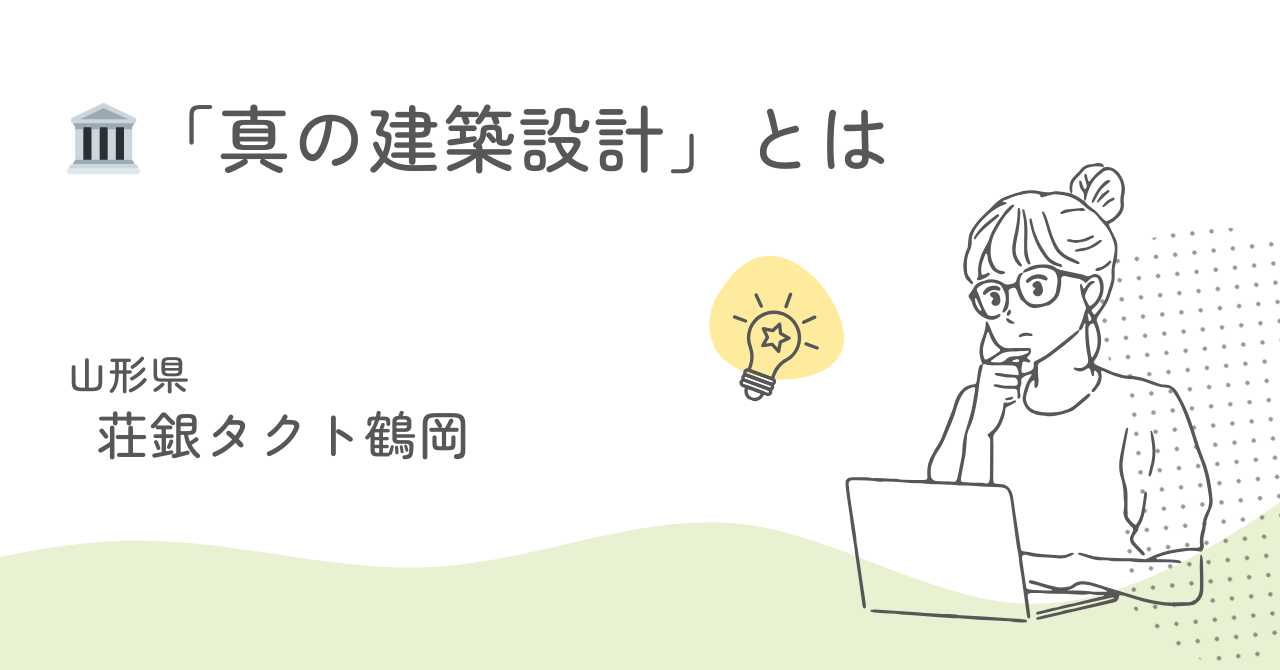この記事では、これまでの経験から見えてきた「こんな入居者には気をつけたい!」という5つのパターンと、それぞれにどう対応すればいいかという実践的なヒントをお届けします。
目次
◆「こんな入居者には気をつけたい!」という5つのパターン
【1】家賃トラブル系|“払えない”ではなく“払わない”
わたしたち大家さんにとって、もっとも多く、そしてもっとも厄介なのが家賃トラブルです。
最初は礼儀正しく、対応も丁寧だった方が、入居して数か月もすると毎月のように、支払いが遅れ、最終的には連絡が取れなくなってしまった…。そんなケース、実は少なくありません。
一度滞納が始まると、それを回収するのはとても大変です。たとえ保証会社が入っていても、支払いが止まるまで時間差があることも。精神的にも大きな負担になります。
✅ 対策ポイント:
-
金額よりも「支払いの姿勢」をチェック
-
保証会社は内容まで確認を
-
申込時のやりとりから人柄や対応力を見ておく
【2】高齢単身系|突然の連絡不通、どうする?
高齢の入居者の場合、健康上の不安や孤独死のリスクがついてまわります。
以前、80代の入居者さんが数日間ポストを開けておらず、部屋からの応答もない状態が続きました。不安になった近隣の方から連絡があり、警察立ち会いのもとで室内を確認することになったことがあります。
結果的に大事には至りませんでしたが、こうした対応は時間も心労も大きく、入居者本人の安全確認の重要性を改めて感じさせられました。
✅ 対策ポイント:
-
緊急連絡先は2人以上、できれば家族に
-
見守りサービスや自治体との連携も視野に
-
保証人の年齢も確認しておく
【3】文化・生活習慣のギャップ系|ルールの“前提”が違う
外国籍の方とのやり取りでは、文化や習慣の違いがトラブルにつながることがあります。
ある入居者さんは、母国では分別の習慣がなかったため、ゴミを曜日やルールに関係なく出してしまい、地域の自治会から強いクレームが寄せられました。また、夜遅くの電話や調理音なども、隣人との摩擦に発展する原因に。
これは本人に悪意があるわけではなく、ただ「文化の前提が違う」ことから起きるすれ違い。だからこそ、最初にきちんと伝えることが大切です。
✅ 対策ポイント:
-
入居前に、生活ルールを多言語で丁寧に説明
-
外国人対応に慣れた管理会社と連携
-
「何が当たり前か」は人によって違うと心得る
【4】生活マナー問題系|契約内容があってないようなもの?
単身者向けの契約で入居された方が、気づけば恋人とペットと3人暮らし…。
私の物件でも、こうした“契約内容と実態のズレ”によって、他の入居者から異臭や騒音に関するクレームが続出したことがありました。確認したところ、入居者本人は「大したことじゃないと思っていた」と悪気のない様子。
こういった事態は、最初の契約時にしっかりとルールを伝えていないと起こりやすいです。曖昧な約束ではなく、具体的に示すことがとても大事なんです。
✅ 対策ポイント:
-
契約時に「禁止事項リスト」を渡し、明記+署名
-
LINEなどで定期的にコミュニケーションを
-
違和感を放置せず、早めの確認と声かけを
【5】特殊ケース系|見えにくいリスクに注意
見た目や申込書の情報だけでは判断が難しい、いわゆる“グレーゾーン”のリスクもあります。
たとえば、SNSで活動している配信者の方が入居した結果、深夜の配信による騒音や、物件前にファンが押しかけてくるという問題が発生。あるいは、精神的に不安定な方が夜中に大声を出したり、近隣に迷惑をかけてしまうケースも。
こうした問題は、申込時点では見えづらいため、事前のヒアリングや会話の中で感じる「違和感」を見逃さないことがポイントになります。
✅ 対策ポイント:
-
「なんとなくの違和感」を大切に
-
SNSなど公の情報もチェック
-
貸さない判断が“守ること”になる場合も
◆ トラブルを防ぐための3つの基本
-
入居前の審査で“人柄”重視
→ 年収や職業だけでなく、言葉づかいや反応を見よう -
契約内容は明文化し、曖昧さをなくす
→ ペットNG、DIY禁止など、具体的に書いて確認を -
入居後の関係づくり
→ 定期連絡やちょっとした声かけが、早期対応につながる
◆ 基本にあるのは“借主保護”の考え方
実は、日本の法律では、賃貸契約において「借りる人=入居者」の権利がとても強く守られているんです。
「住まいを失う」というのは、生活の基盤を失うこと。
だから民法や借地借家法では、入居者の立場が保護されるようにルールが作られています。
そのため、トラブルがあったからといって、「はい、出ていってください」というわけにはいきません。もし退去を求める場合は、法律に沿った手続きが必要で、時間も手間も大きくかかってきます。
だからこそ、「あとで対応する」ではなく、「最初にちゃんと見極める」が、いちばんの対応になるんです。
◆不動産屋・保証会社に丸投げしない
入居募集や、入居審査は不動産屋さんや保証会社さんにお願いするのが主流です。それは構わないのですが、それに安心して丸投げしてしまうのは、実は危険です。
大家さんとしても情報を集めてなるべくリスクをなくするための対策をご自分で取ることが大事です。
わたしも、わたしなりのルールを設け、不動産屋さんや保証会社さんと共有しています。そこに合致しない人は「入居をお断り」するという選択肢もあると思っています。
そして、大家さんの意向を汲み取り、寄り添ってくれる業者さんとお付き合いするというのも大切です。
◆ まとめ|“人を見る目”が最大の資産
ここまでご紹介した5つの入居者トラブル事例、ひとつでも「うちもあり得るかも…」と思った方は、決して他人事ではないはずです。
賃貸経営において、入居者との関係は、単なる“契約相手”ではなく、暮らしと安心を共に築く“パートナー”のような存在です。だからこそ、契約前の審査やヒアリングは、義務感ではなく“未来の自分を守る大事な工程”だと思って丁寧に向き合ってほしいなと思います。
とはいえ、「人を見る目」に絶対的な正解はありませんし、相性や運の要素もゼロではありません。だからこそ、知識と経験、そして“線引き”をもって判断できるかどうかが、トラブルを未然に防げるかどうかの分かれ道になります。
そしてもうひとつ大切なのが、バランス感覚です。あまりに厳しく選びすぎれば空室が続き、収益に影響が出てしまう。でも、妥協しすぎると、あとから大きなストレスや損失になって返ってくる。
この“ちょうどいい塩梅”を見つけるのが、実は一番難しいところかもしれません。
だから私は、ひとりで悩まず、いろんな大家さんの実例や工夫に触れることがとても大事だと考えています。「身の丈大家さん」のコミュニティでは、まさにそういったリアルな学びや情報共有ができる場をつくっています。
「気になる」「もっと知りたい」という方は、どうぞお気軽にご相談くださいね。
あなたの物件が、安心して長く育っていくことを心から応援しています。
今日の記事はここまで。
大家さんになりたい人、気になっている人は、関連記事もぜひご覧になってくださいね🥰