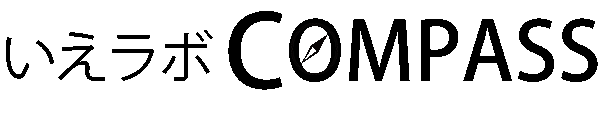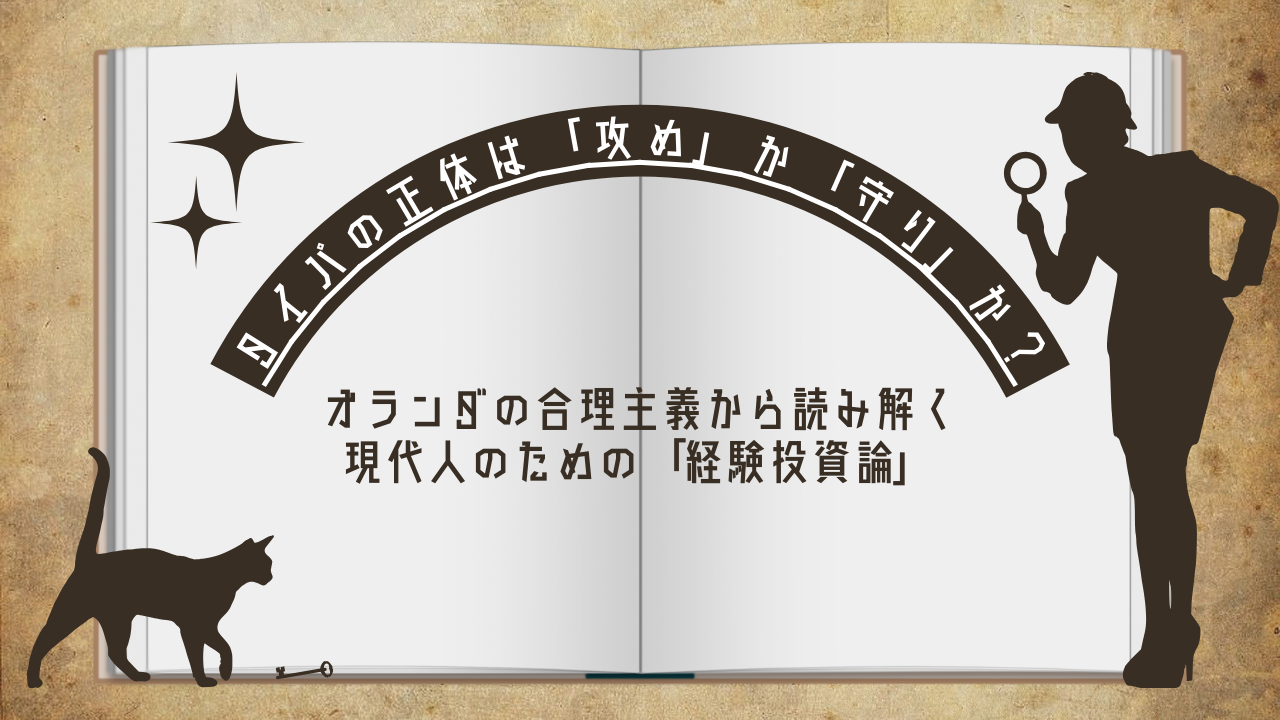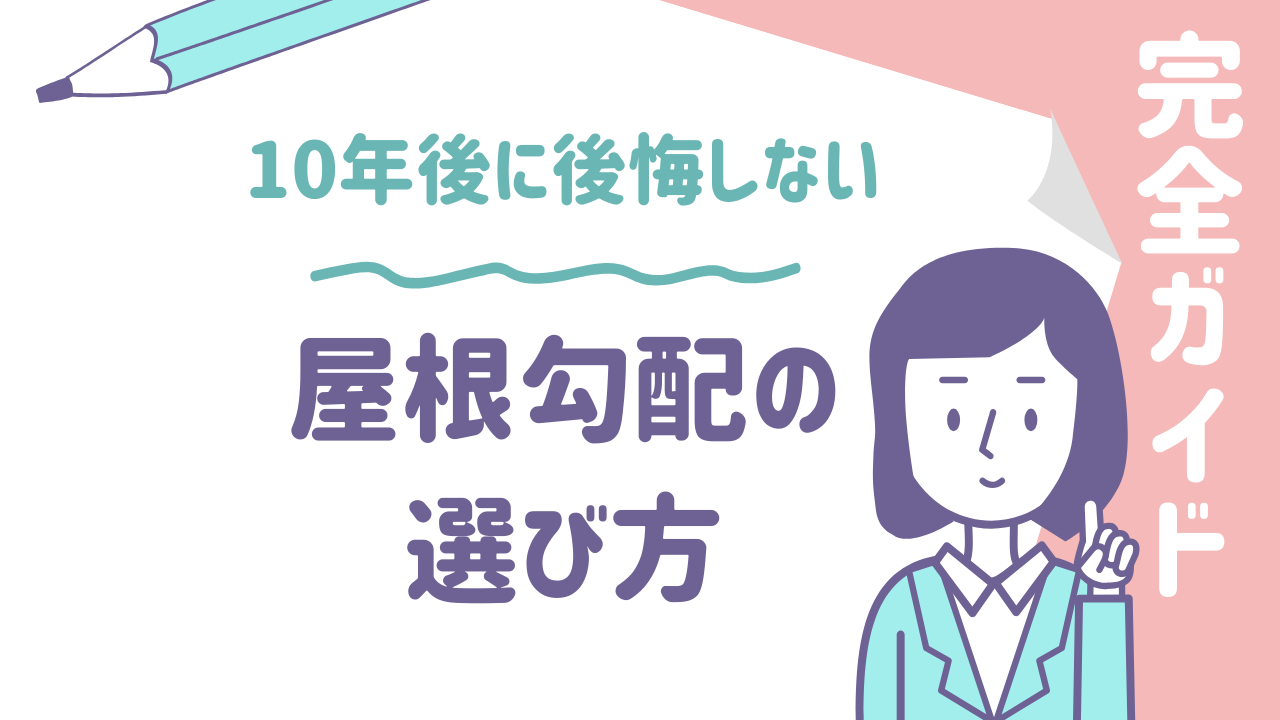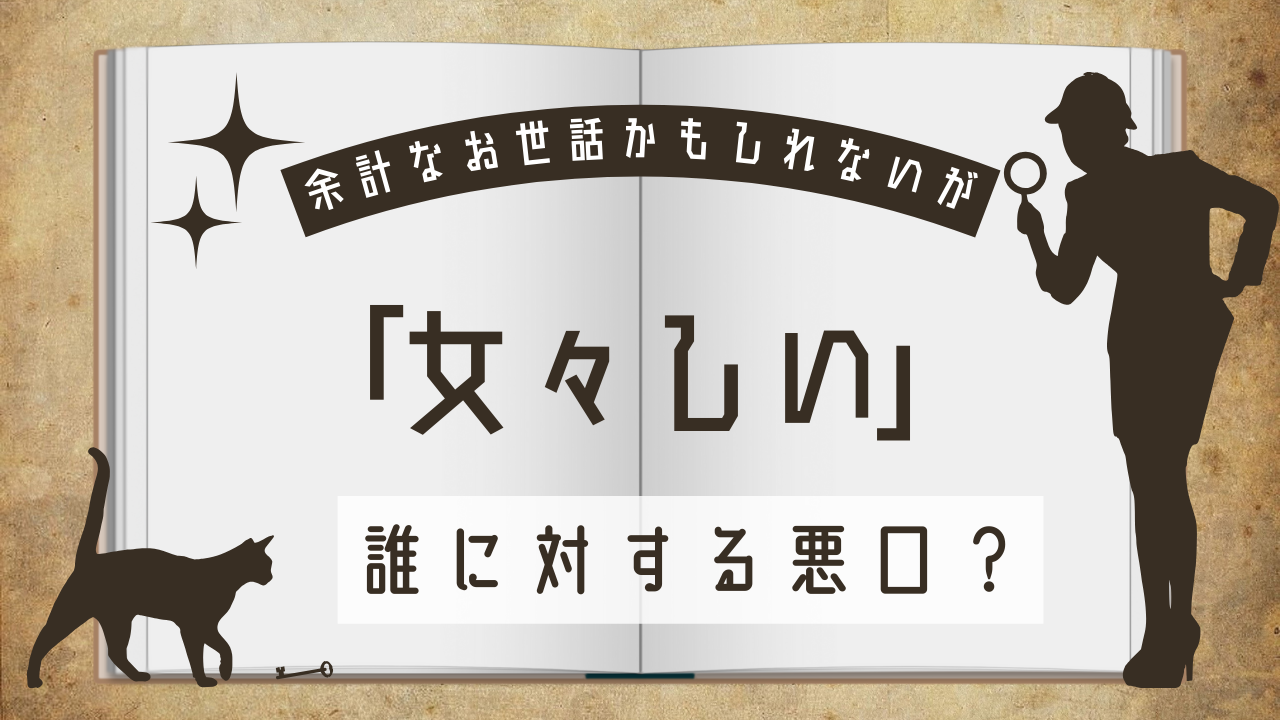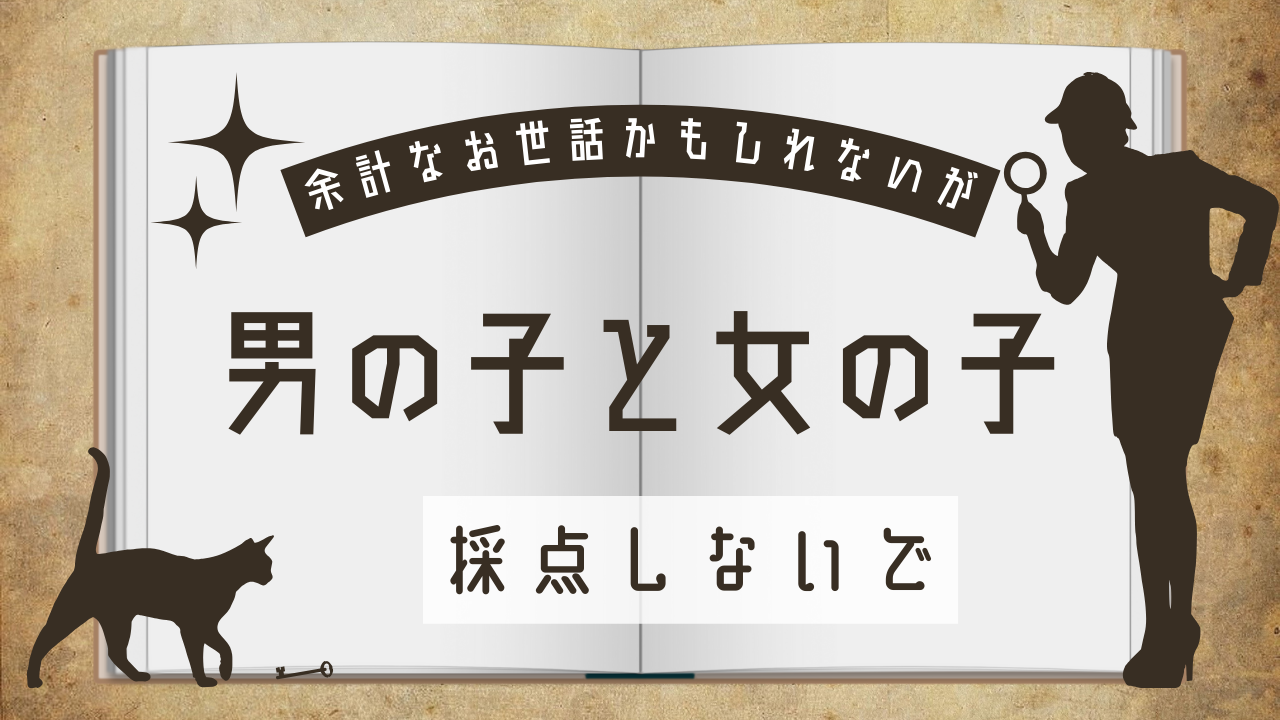不動産賃貸業をやるなら必須の知識、「減価償却」についてくわしくまとめてみました。
目次
減価償却とは
減価償却とは、固定資産の取得価額を法定耐用年数にわたって分割し、毎年の費用として計上する会計処理のことを指します。これにより、不動産の取得費用を一度に経費として計上するのではなく、長期にわたって分散させることで、税務上の利益を調整することが可能になります。
減価償却の対象資産とタイミング
(1) 土地と建物の区分
不動産の購入時には、土地と建物の取得価額を明確に分ける必要があります。土地は減価償却の対象外であり、建物のみが減価償却の対象となるため、適切な価格配分を行うことが重要です。
(2) 計上開始のタイミング
減価償却は、資産を使用開始(引き渡し)した月から行う必要があります。不動産賃貸業の場合、賃貸契約が成立し、実際に運用が開始された時点で減価償却の計上を開始します。したがって、契約締結日や引き渡し日を正確に把握することが求められます。
減価償却の計算方法
(1) 定額法
毎年同じ額の減価償却費を計上する方法です。取得価額を法定耐用年数で割り、均等に経費計上するため、長期的に安定した経営計画を立てやすくなります。
(2) 定率法
毎年一定の割合で減価償却費を計上する方法で、初年度に多くの減価償却費を計上し、以降は減少していきます。初期の税負担を軽減できるメリットがありますが、2007年4月1日以降に取得した資産は、原則として定額法が適用されます。
減価償却のメリットとデメリット
(1) メリット
-
税負担の軽減: 減価償却費を経費として計上することで、課税所得を抑え、所得税や法人税の負担を軽減できます。
-
キャッシュフローの改善: 実際の支出がなくても経費として計上できるため、手元資金を圧迫せずに節税効果を得られます。
-
資産管理の適正化: 耐用年数を基準に修繕やリフォームの計画を立てることで、資産価値を維持しやすくなります。
(2) デメリット
-
売却時の税負担増加: 減価償却により帳簿上の資産価値が減少するため、売却時の譲渡所得が増え、譲渡税の負担が大きくなる可能性があります。
-
実際の市場価値との乖離: 減価償却によって帳簿上の価値が減少しても、市場価値が上昇している場合、適正な評価との乖離が生じる可能性があります。
-
計算の複雑さ: 定額法・定率法の選択や適用には会計知識が必要であり、専門家の助言を受けることが推奨されます。
減価償却と税務上の考慮点
(1) 減価償却資産の取得価額
取得価額には、購入価格だけでなく、登録免許税、仲介手数料、リフォーム費用などの関連費用も含める必要があります。これにより、適正な減価償却費の計算が可能になります。
(2) 売却時の譲渡所得税
減価償却によって資産の簿価が下がるため、売却時に計上する譲渡所得が増加し、譲渡所得税の負担が大きくなる可能性があります。売却時の税負担を事前にシミュレーションすることが重要です。
まとめ
不動産賃貸業では、減価償却を適切に活用することで、税負担を軽減し、キャッシュフローを安定させ、長期的な資産価値を最大化することが可能です。特に、建物の取得価額の適正な配分、計上開始のタイミング、定額法・定率法の選択、そして売却時の税務上の影響を考慮することが求められます。
たとえば、築古の中古アパートを購入し、短期間で大きく減価償却を行うことで初期の税負担を抑えつつ、収益を最大化する戦略を取る投資家もいれば、新築物件で安定した定額法を用い、長期的な運用を前提に資産管理をするケースもあります。
どの方法が最適かは、所有する不動産の種類や投資戦略、税務上の影響によって異なります。
制度を正しく理解し、戦略的に活用することで、不動産賃貸業の成功に大きく影響します。
減価償却を味方につけて、より効果的に資産づくりをすることできるといいですね❤️
今日の記事はここまで。
次回は、わたしが運営している、「小さく始めて失敗しない身の丈大家さんのすゝめ」メソッドでお伝えしている、身の丈大家さん的減価償却の活用法を記事にしたいと思います💕おたのしみに😆
ブログの更新やイベントなどの最新情報はインスタグラムのストーリーズでお知らせしていますので、フォローしてお待ちください💕
いいね・シェアもうれしいです😊